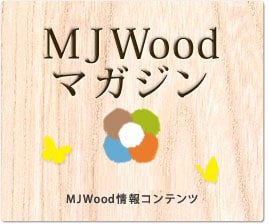![]() 2015.02.27
2015.02.27
親などからの住宅取得資金贈与の非課税枠が拡充!
今年度は政府の住宅支援施策の一つとして、住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡充と延長がきまりました。 生前贈与等の制度を上手に利用できるか、否かで、納める税の額も変わります。 そこで、今回は住宅取得等資金の贈与を受ける場合の「特例」と「注意点」についてご紹介します。

住宅取得等資金贈与の特例を上手に活用しましょう。
■「住宅取得等資金贈与の特例」とは何でしょう。
今回は、「住宅取得等資金贈与の特例」の仕組みについて紹介します。
住宅を購入したいと思ったとき、自己資金準備の問題は悩ましいですよね。「なるべく早く買いたいけれど、頭金が十分に貯まっていない・・・」。そんなときに検討したいのが、「住宅取得等資金贈与の特例」です。
親から子へ、祖父母から孫へ、マイホーム取得等のための資金を贈与する際に、通常の贈与(暦年課税等)とは別に贈与税を非課税にする枠を設ける、というものです。期間限定の制度ですが、平成27年度以降は延長&拡充されることが発表されました。
■「贈与税の非課税措置が延長&拡充」されます。
昨年末まで最大1,000万円であった贈与税の非課税措置が、平成27年中の贈与であれば、平成28年3月15日までに引き渡し(または棟上げ状態になっている)が完了し、同期日内に申告すれば、贈与を受けた人1人につき、質の高い住宅で1,500万円まで、その他の住宅で1,000万円までの贈与が非課税になります。暦年課税の基礎控除110万円と合わせて使えるので、贈与を受ける人1人あたり1,610万円(質の高い住宅の場合)、または1,100万円(その他の住宅)までの贈与に関しては贈与税がかからないことになります。
| 契約年 | 質の高い住宅 | 左記以外の住宅(一般) |
| 平成27年 | 1500万円 | 1000万円 |
| 平成28年1月〜28年9月 | 1200万円 | 700万円 |
※消費税増税後で、消費税10%物件を購入された方は、消費税増税の需要の冷え込みを避けるため非課税枠が増額されます。
■住宅の種類によって非課税額が変わります。

「住宅取得等資金贈与の特例」を受ける際に、住宅の種類によって非課税額が変わります。
「質の高い住宅」は「一般の住宅」より非課税額が大きくなります。
平成27年は
・「一次エネルギー消費量等級4以上」または「高齢者等配慮対策等級3以上」という要件が増えています。
4つのうちの1つでも、満たしていれば「質の高い住宅」となります。どれも満たしていないものが「一般の住宅」です。
■受贈者の要件は?
<住宅取得等資金贈与の特例の主な要件>
| 誰から(贈与する人) | 父母および祖父母等の直系尊属 |
| 誰に(贈与受ける人) | 贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の子ども・孫等の直系卑属(合計所得金額2,000万円以下) |
| 住宅取得等の主な要件 | 平成27年1月1日〜平成27年12月31日の贈与で翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です |
| 対象住宅等の主な要件 | 自己の居住用家屋およびその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。50m²以上240m²以下で、かつその床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されているものであること ・木造は築後20年以内 ・耐火建築物は築後25年以内 ・新耐震基準適合証明された住宅(既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の一定の住宅を含む) |
■住宅資金贈与を受ける場合の注意点
この制度を利用する場合の注意したい点が2つあります。
① 契約前に、棟上げ・引き渡し時期を確認する
② 住宅資金をもらった時期が記録に残るようにしておく
これから家を建てるという場合は棟上げ(屋根が完成している状態)のタイミングを、建売住宅を購入する予定なら、引き渡し時期がいつになるかを必ず確認しましょう。
たとえば、平成27年3月に実父から500万円の贈与を受けて、現在工事中の建売住宅の売買契約を締結したとしましょう。平成28年2月に引き渡され、同年3月15日までに贈与税の確定申告を行ったら、平成27年贈与分の特例が適用されます。しかし、平成28年4月の引き渡しとなると、平成28年贈与分として控除額になります。親や祖父母からの贈与をもとにマイホームを取得する場合は、請負契約や売買契約を結ぶ前に棟上げ状態になる日、または、引き渡し日を必ず確認しましょう。

■二世帯住宅を建てる方には様々なメリットが考えられます
住宅を新築する際に、親世帯が暮らしていた土地に二世帯住宅を計画される方も多いと思います。
人が増えれば、費用だって分担できます。建てるときも、暮らしてからも。
土地の費用を建物にまわせるなど、単世帯で建てるよりも金銭面の負担が減るだけではなく、税制上の特例を上手く使って二世帯住宅などを建築すれば、ご自身は、より大きな住宅をより少ない負担で計画することも可能になります。
親子で資金を出し合う場合に、二世帯住宅は、父と子で登記することになります。「住宅取得資金の贈与の特例」を使って、父から子へ贈与し、子はその贈与を受けた金額を、住宅購入の資金に充てるものとします。父に相続が発生した場合には、父の持分のみが相続財産となり、相続税も節税できます。
金銭面のメリットだけではありません。二世帯住宅にすれば、通勤時間も短縮できるかもしれません。暮らす人数も増えます。人数が多い方が、家事や育児など、さまざまな用事を分けあうには断然有利です。みんなで集まって食事をしたり、会話する時間が長くなったり、ちょっとした外出時に子どもの面倒をみてもらったり、様々なメリットが享受できます。何かあったときや将来介護が必要になったときも、心強いでしょう。子世帯のママも仕事と育児の両立もスムーズになります。

■さらに相続時精算課税度の非課税制度も活用できます。
平成27年中に贈与を受けた場合には、住宅取得資金の非課税枠1500万円(質の高い住宅の場合)+相続時精算課税制度の非課税枠2500万円がダブルで使え、4000万円を、贈与税なしで贈与することができます。
さらに、夫と妻が、それぞれの親から、この制度を使って贈与を受けて住宅を取得し、その住宅を夫婦で共有とした場合には、最大で8000万円を、贈与税なしで贈与できることになりますので、最大限活用することも考えてみましょう。
ただし、相続時精算課税制度の2500万円については、贈与時には贈与税がかかりませんが、相続が発生した時には、相続財産に含めて相続税を計算しますので、相続税の節税にはなりませんのでご注意下さい。
資金面で制度が使えるのはいつまでなのかなど、専門家とも相談したうえで、これらの特例を上手に利用したいですね。
「そろそろ住宅が欲しいなぁ・・・」「消費税がまた上がる前に・・・」などと、お悩み中の皆様、それぞれの制度の特徴を理解した上で、先を見越した、早めの検討スタートがおすすめです!