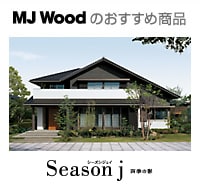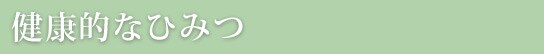
アレルギーの原因になったり、思わぬ病気を引き起こすこともあるのが、家の中にひそむカビやダニ、細菌です。檜の精油成分であるテルペン類には、カビやダニの繁殖を抑える作用や、細菌の発生を抑える効果があります。実験によると、檜の木屑の中ではダニが死滅してしまうそうです。医学の分野では、院内感染で問題視されるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の発育を阻止する効果があるという研究結果も発表されています。

日本には、檜で建てられた家に住むと「風邪をひかない」とか「3年間は蚊がやってこない」という言い伝えがありました。お寿司屋さんのカウンターや飯台(寿司桶)、ネタ箱も、その多くは檜製です。生ものを扱うまな板にも、昔から檜が使われてきました。日本人は、経験的に檜の抗菌作用を実感していたからこそ、暮らしの中で広く利用してきたに違いありません。檜は「健康」という側面を考えても、すぐれた特質を備えた木です。

高温多湿な夏があり、寒く乾燥した冬がある、日本の気候。湿度が高すぎたり、低すぎたりする状態は不快で、健康にとってもマイナスです。木は、空気中の湿度が高いときには水分を吸収し、湿度が低くなれば水分を放出するという調湿機能を備えています。木造の家は自然に湿度を調節し、快適な室内環境を保ってくれます。また、構造体を傷める結露も比較的少ないため、家族だけでなく、家そのものの健康を保つにもメリットがあります。
木が調湿機能を備えているとはいえ、住宅の構造材となる木材にとっては、湿気自体はやっかいな存在です。湿気の被害で最も深刻なのは、木材を腐らせていくこと。ところが檜は、浴槽やまな板にも使われているように、もともと湿気や腐朽に強い木です。檜の精油成分には、木材腐朽菌であるオオウズラタケやカワラタケの繁殖を抑制する働きがあることがわかっています。檜こそ、高温多湿な夏がある日本に最適な木材といえるでしょう。