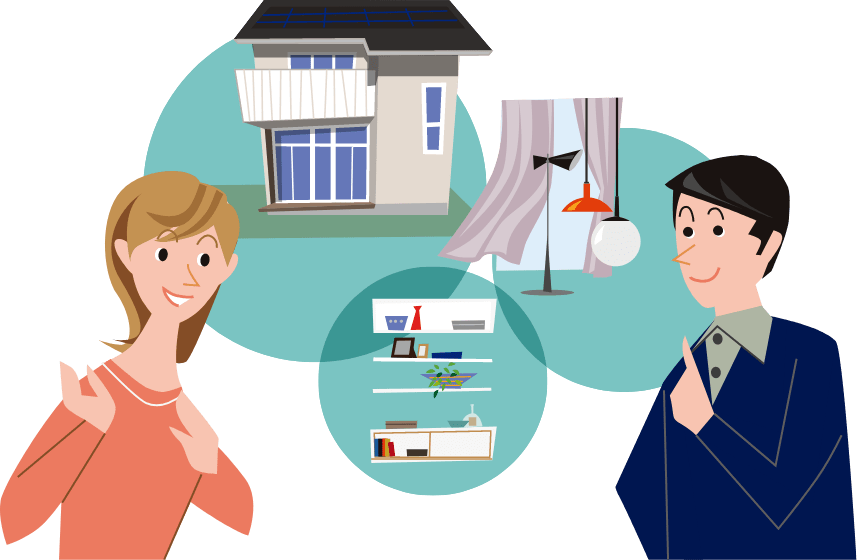interview
子どもに本との
出合いをつくろう
ブックディレクター
幅 允孝さん
本のチカラを信じて、
あらゆる場所で本と人との出合いを
生み出し続けてきた
ブックディレクター・幅 允孝さん。
子どもが本を好きになる
出合い方について伺った。
-

-
- 小さい頃から読みたい本を読む
- 親から「これを読みなさい」と強要されることはなく、おこづかいも本だけは別。しかも本屋はツケ払いができたというのどかな環境でした。児童文学、雑誌、マンガ、図鑑などジャンルを問わずに、小さな本屋を泳ぐように、そのとき興味のある本を自由に読み進めていました。自分が「おもしろい」と感じたものを他の人に伝えたい。その想いは当時からで、本屋に人が来ない時代に、人がいる場所に本を持ち込む仕事をしています。
本には書き手の想いが宿っていきます
紙の本はネット上の情報と比べ、一度世に出てしまうと、書き直しをすることができません。装丁や印刷など出版に関わる誰もが責任を負います。だから、推敲に推敲を重ねるうちに本そのものが熱を帯びて、書店に並ぶまでには書き手の想いが宿っていきます。出所があやふやな情報が氾濫している世の中で、出自が明白な本という存在は頼りになりますし、深く心に刺さる可能性が高いのではないでしょうか?
興味がない人に、本を届ける
人間というのは本来、本に興味がなくても生きていけます。しかも「今日は何が食べたい?」というのと同じように、読みたい本は時々の気分で変わるもの。それを前提として、本から縁遠くなっている人たちに、"本を読むことでしか得られない心が動く経験"をどうやって提案できるかを考えています。
-

-
- 子どもと本との自由な出合い
- 長男が2歳くらいのとき、アンリ・マティスの「Jazz」という作品集を偶然ながめていました。そのとき、彼は鮮烈な切り絵の色彩の中に赤色を見つけては、「あか!」という言葉とともに指差して遊んでいました。そのうちに道具箱から赤のクレヨンを持ち出してきて、赤色の上に重ねて塗り始めました。子どもは著者の偉大さや、本の背景にある文脈などに捉われることなく、心が動いたものに興味を示します。だからこそ、無垢な目で見ることができる時期にあらゆる種類の本に、自由に触れることは大切なことだと思いました。
-

-
- 子どもを、子どもと決めつけない
- 山形県鶴岡市に、「KIDS DOME SORAI」という屋内外一体型の遊戯施設が、2018年11月1日に開業しました。その選書のコンセプトは、「大人は子ども、子どもは大人」。ライブラリには、子どもが読む本はこうあるべき...と決めつけない本選びを仕掛けています。子どもは、子ども扱いされることを嫌いますし、子ども目線でのおもしろさがある。対象年齢などに捉われ過ぎず、好奇心の赴くままに読めばよいのです。
自分の芯になるものをつくる
ちょっとした調べ物は外部記憶が代行してくれる時代です。一方で、読書は心を駆動させ、深く自分に刺さって残り続ける痕跡をつくるものだと思います。いつ芽が出るか、そもそも芽が出るかどうかもわからない。遅効の本というメディアだからこそ、自身の野性と直感を信じて、好きに本を手に取ればいいと思います。そもそも読書に正解も間違いもないのですから。
-

-

-
- 自分の大切な本を並べた本棚をつくる
- 子どもに「読書と親しんでほしい」と考えるのであれば、大好きな本を置いておく本棚を、設けてみてはどうでしょうか。自分の来歴を示す鏡となりますし、ネット上のクラウドでなく体に近いところにあるものほど、安心して忘れることができます。さらに、「ここの本は読んじゃダメ」と言ったりすると、意外に子どもが手にしたりします(笑)。
子どもが本に慣れるためには
幼児期にたくさん絵本を読み聞かされた子どもが、すんなり文章だけの児童文学に親しむかと言うと、残念ながらそうではありません。近年はそのジャンプができない子も多いので、絵本の次は幼年童話で文字に慣れていくとよいでしょう。『魔女の宅急便』に行く前に、『おばけのアッチ』シリーズを挟んでみるというイメージです。少しずつ絵を文字に置き換えていくことで、頭の中にイメージを膨らませる経験が身についていきます。
親子で本に親しんでほしい
現代は、誰もが限られた時間の中で何をするべきかという選択に迫られます。それでも、親が本を読む時間を堪能している姿を見ていれば、ページをめくる行為が楽しいものだと子どもたちに伝わり、読書が身近な存在になります。たとえば土曜の午前中にジムへ行くように、親子で読書を楽しむ時間を設けてはいかがでしょう。子どもも大人も、人生を健やかに生きていく相棒として、その傍に本があるといいですね。
-

profile

- 幅 允孝さん
- ブックディレクター。BACH(バッハ)代表。愛知県津島市生まれ。ホテルや病院、企業オフィスなど、あらゆる場所で本と人が自然に出合うための環境づくりを行う。最近では、本のディレクションを行うほか、自身も編集や執筆を手掛けている。
関連サイト
BACH