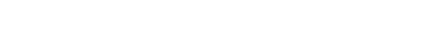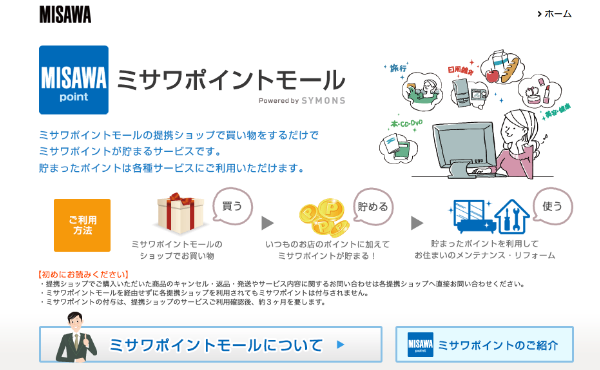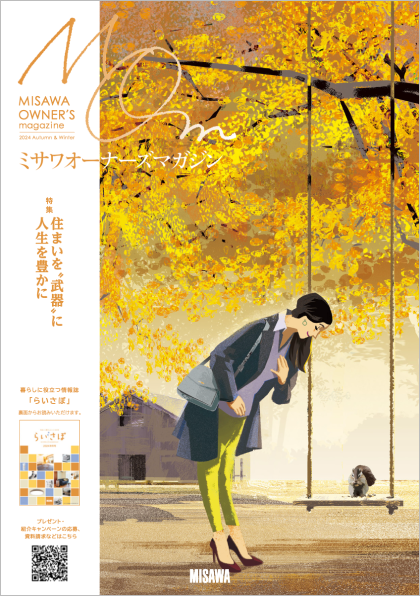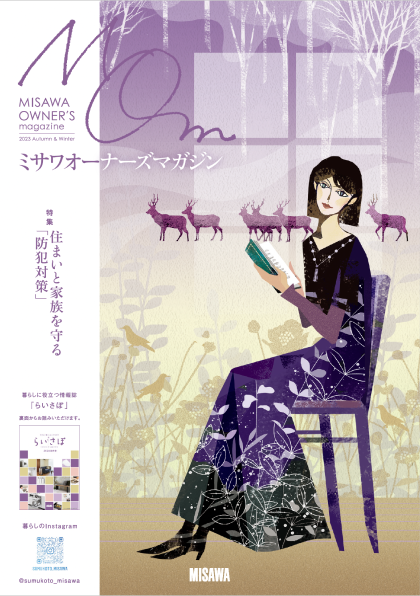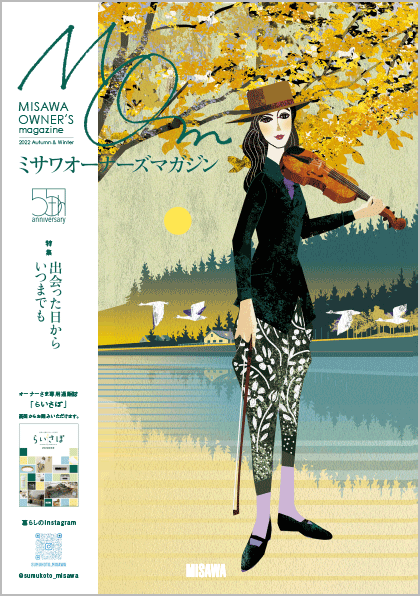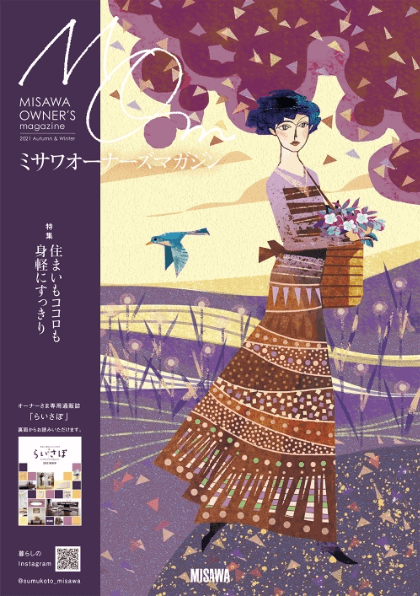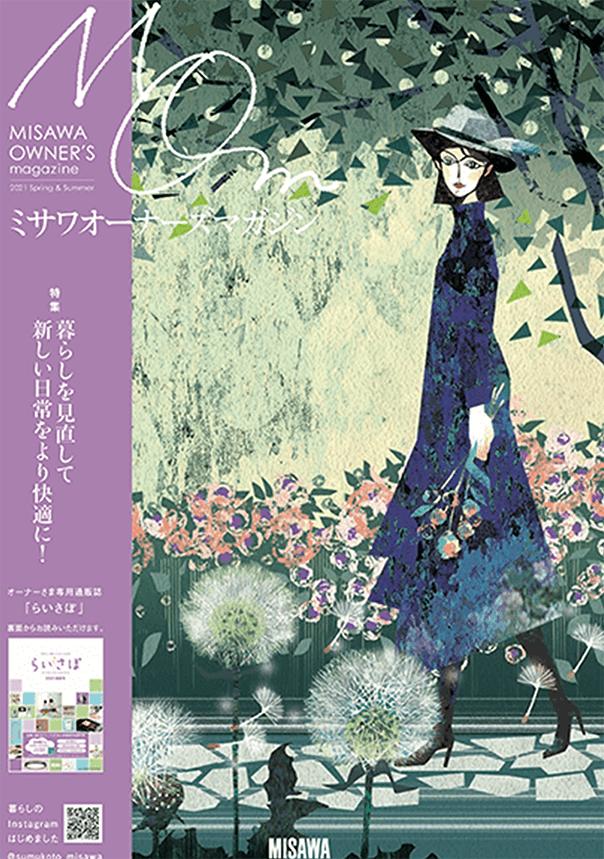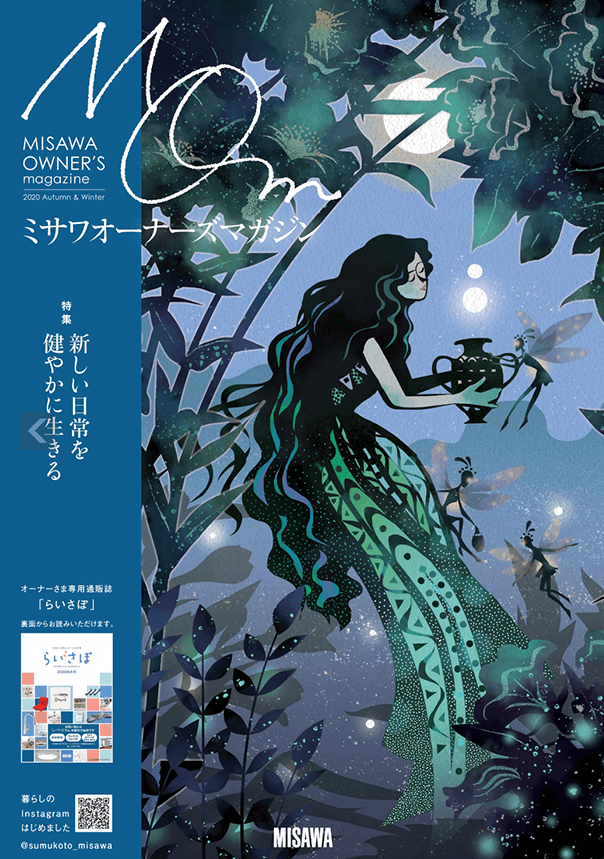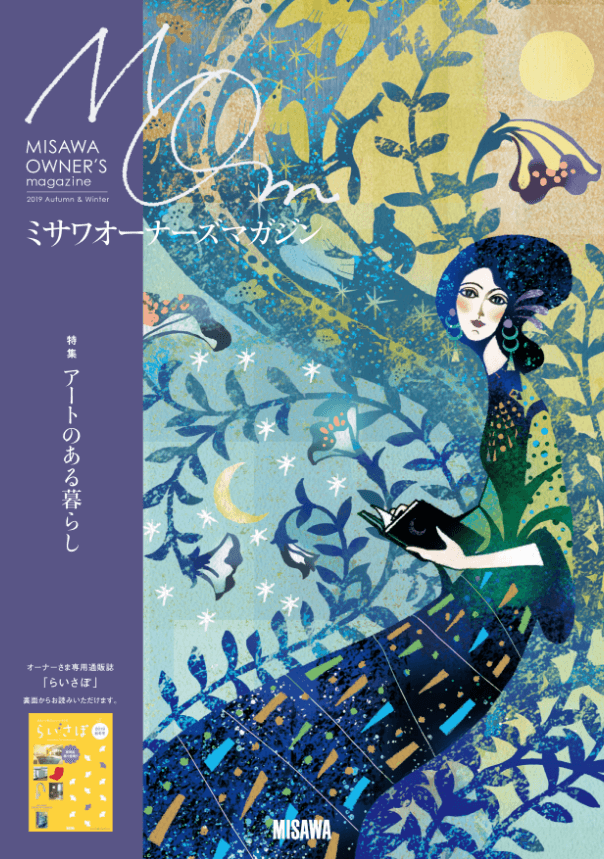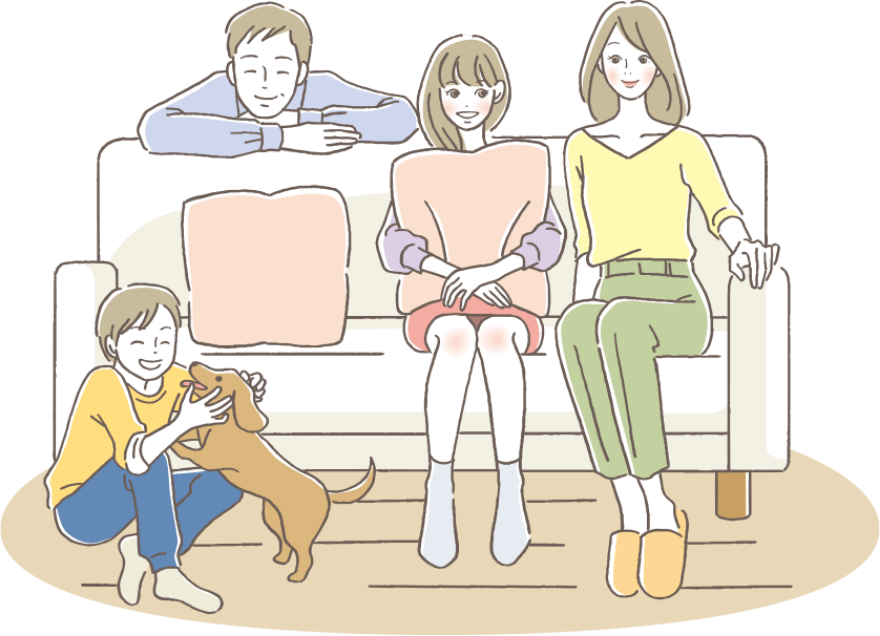
第3回
新しい暮らし方で、
住まいのカタチはどう変わる?
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために定着しつつある「新しい生活様式」。テレワークの普及で加速する「職住融合」によって、暮らし方はどう変化するのでしょうか。これからの住まいのカタチについて、社会デザイン研究者の三浦展さんにお伺いしました。

三浦 展さん
みうら あつし
社会デザイン研究者。カルチャースタディーズ研究所主宰。1958年生まれ。1982年、一橋大学社会学部卒業後、(株)パルコ入社。マーケティング情報誌『アクロス』編集室に勤務し、後に同誌編集長。1990年、三菱総合研究所入社。1999年、カルチャースタディーズ研究所設立。消費社会、家族、若者、階層、都市などの研究を踏まえ、新しい時代を予測し、社会デザインを提案している。『下流社会』(光文社新書)、『第四の消費』(朝日新書)など著書多数。近著に、『愛される街』(而立書房)、『コロナが加速する格差消費』(朝日新聞出版)などがある。
――コロナ禍で在宅勤務が増えています。ミサワホームでは2013年に、在宅でも働きやすいよう、リビングに隣接したコンパクト空間「ミニラボ」や、家族がつながり学びあう「ホームコモンズ」などを提案してきました。コロナ禍で人々が住まいに求める条件はどのように変化したのでしょうか。
三浦男性も女性もフルに働く。コロナ禍をきっかけに在宅勤務が普及したことにより、日本もやっとそんな社会に変わりつつあるのか、という印象ですね。実際、通勤に便利な都市部に住む必要がなくなったことで、従来よりも広い郊外の家に移り住み、仕事部屋を確保する人も増えてきました。さらに言えば、我が家もそうですが、夫婦ともにフルタイムで仕事をしていて、子どもも社会人に成長した家庭では、家族みんなが在宅で仕事をすることになりますから、それを前提とした家づくりをしておく必要があります。


仕事や趣味に集中できて、家族とのつながりも豊かな「ミニラボ」
15年前にアメリカの郊外住宅地を視察したとき、各部屋にLANのジャックがあり、間取り図を見ると、階段の広い踊場に「カフェ」と書いてありました。現地ではすでに各部屋で在宅ワークができるのは当たり前で、そのうえ仕事の合間に気軽にくつろぐ「カフェ」という「第三空間」まで用意されていたわけです。これには驚きました。
――在宅ワークで加速する「職住融合」は、私たちの暮らし方やまちとの関わりにどんな影響を与えるのでしょうか。
三浦家にいる時間が増えたことで、いつもなら職場にいる時間帯に自宅周辺へ出歩くようになり、自分の住むまちを新しい目で見るようになった人が、特に男性に多いと思います。「こんなところに理髪店があったのか」「この古書店の存在は知らなかった」など、おもしろそうなお店を発見し、まちの魅力に気づく機会が増えたのではないでしょうか。逆に、物足りなさを感じるまちもあるかもしれませんね。たとえば、夕暮れ時に焼き鳥でちょっと一杯やりたいのに一軒もないとか……。
これからはまちの充実度が問われますから、住民の一人としてエリアの魅力を高めていくことも大事になりそうです。私が理想とするのは、個人が自宅を改装してカフェを開く、あるいはシェアオフィスをつくるといった、住民が主体のムーブメントが起きることです。自分の住まいを外へ開くことで、地域に新たなコミュニティが生まれ、それによって街の価値も高まっていくと思います。
これからはまちの充実度が問われますから、住民の一人としてエリアの魅力を高めていくことも大事になりそうです。私が理想とするのは、個人が自宅を改装してカフェを開く、あるいはシェアオフィスをつくるといった、住民が主体のムーブメントが起きることです。自分の住まいを外へ開くことで、地域に新たなコミュニティが生まれ、それによって街の価値も高まっていくと思います。


2013年に発売された「GENIUS GATE」は、外へ「住み開く」がコンセプト。二世帯住宅の新しい在り方の一つとして、近隣へ開き、つながる仕掛けを提案しています
――在宅時間が長くなった結果、DIY消費が急増するなど、既存の家のあり方を見直す人が多くなりました。
三浦毎日通勤していた人は、家に対してそれほど関心が高くなかった人も多かったのではないかと思います。在宅ワークで在宅時間が増えると、家に対する意識も変わります。これまでの住まいでは満足できず、DIYで好みの住空間に変えたり、あるいは庭に木や花を植えたりと、手を加える楽しみに気づくわけです。コロナ禍を機に、家も「自己表現」のひとつとして、カスタマイズする人がどんどん増えていくといいですね。
さらに、たとえば自分らしくリフォームした家をご近所に披露する機会を設ければ、それをきっかけに地域とのつながりが生まれると思います。私が魅力あるまちを見分けるポイントとして注視していることがあります。それは手づくりの表札や郵便受けの家が多いかどうか。個人が自分らしい表現を大切にしているまちって、自由でアートな雰囲気を醸していて楽しそうだと思いませんか。
さらに、たとえば自分らしくリフォームした家をご近所に披露する機会を設ければ、それをきっかけに地域とのつながりが生まれると思います。私が魅力あるまちを見分けるポイントとして注視していることがあります。それは手づくりの表札や郵便受けの家が多いかどうか。個人が自分らしい表現を大切にしているまちって、自由でアートな雰囲気を醸していて楽しそうだと思いませんか。

――最近は都市部に住みつつ、郊外での活動拠点を設けるとなどの「2拠点生活」も増えていますが、この傾向をどのようにご覧になっていますか。
三浦私の場合も新潟県上越市にある実家が空き家になっているので、実家を活用して2拠点生活を始めようと、今ちょうど東京の事務所の書籍や仕事の資料をどんどん新潟に送っているところです。また、京都の友人がリノベーションで部屋を用意してくれるという申し出もあるので、ひょっとすると3拠点生活になるかもしれません。仕事によってはリモートで取材や打ち合わせが可能な場合もあり、どこにいても仕事ができますし、新幹線を使えば移動もスムーズです。東京などの都市部と地方の2拠点居住を選ぶ人は、これからさらに増えるのではないでしょうか。地方の活性化につながる可能性もあり、まちや暮らしがこれからどう変化していくのか、楽しみにしています。

新しい日常に合わせたリフォームなどもご紹介しています。
お得なサービス- SERVICE -
おすすめコンテンツ- RECOMMEND -
バックナンバー- BACK NUMBER -
※掲載内容は本誌発刊当時のものとなります。
ミサワオーナーズクラブへの
お問い合わせ
0120-507-330
9:00〜18:00(土日祝・年末年始を除く)