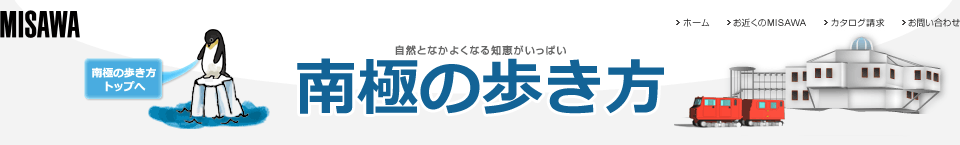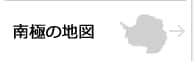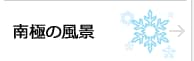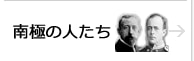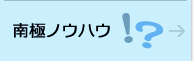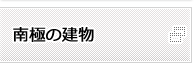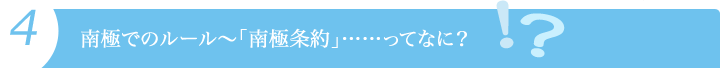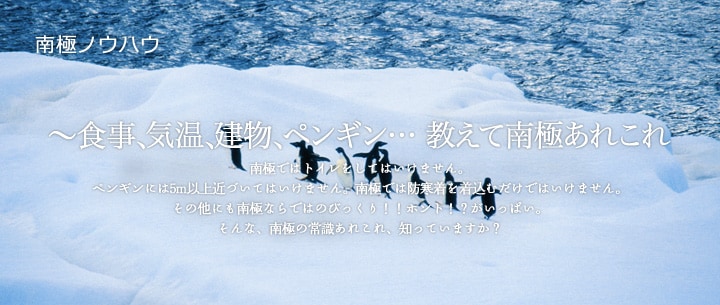
 「ペンギンやアザラシに近づいてはいけない」とか「南極からは一切のものを持ち去っていけない」とか、南極に関する様々なルールは、「南極条約に定められている」と説明されていますが、そもそもこの“南極条約”とはいったい何なのでしょう?
「ペンギンやアザラシに近づいてはいけない」とか「南極からは一切のものを持ち去っていけない」とか、南極に関する様々なルールは、「南極条約に定められている」と説明されていますが、そもそもこの“南極条約”とはいったい何なのでしょう?
現在の南極は、どの国にも属さない地球上で唯一の場所となっていますが、南極大陸が発見され、その存在が明らかになった当初は、南極も他の土地と同様、南極地域を探検した国や近隣国などによる領土権争いの対象でした。1908年にイギリスが南極一部地域の領有を主張すると、それを切っ掛けに他の国々も南極地域の一部領有を主張し始めたのです。
しかし、その一方で各国の科学者たちの間では、極地(南極および北極)を国際共同研究の場にしようという機運が高まりを見せていました。その流れは、国際観測キャンペーン「国際極年(International Polar Year)」として結実し、南極における国際的な協力体制へと本格化されていきました。第1回(1882〜83年)、第2回(1932〜33年)と続いた「国際極年」は、極地以外の総合的な地球物理学観測の計画にまで拡張されて、「国際地球観測年(International Geophysical Year)」(1957〜58年)に引き継がれることとなります(話は少しそれますが、日本がこの国際地球観測年に参加するために編成した、後に第1次南極地域観測隊と呼称を変更する南極地域観測予備隊が、現在まで続いている南極地域観測隊の始まりとなっています)。
そして、この国際科学研究プロジェクトにおいて実施された国際的な科学協力体制を維持、発展させるため、日本、アメリカ、イギリス、ソ連などの原著名国12カ国により、『南極条約』は採択されました。
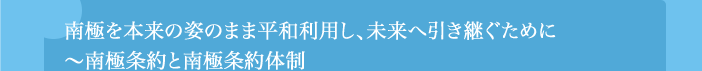
 南極地域(南緯60度以南の地域に適用)の継続的な平和利用を目的とした南極条約は、南極地域の平和的利用(軍事基地の建設、軍事実習の実施等の禁止)、科学的調査の自由と国際協力の促進、南極地域における領土権主張の凍結、南極地域に関する共通の利害関係にある事項について協議し、条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催、などを主な内容としています。
南極地域(南緯60度以南の地域に適用)の継続的な平和利用を目的とした南極条約は、南極地域の平和的利用(軍事基地の建設、軍事実習の実施等の禁止)、科学的調査の自由と国際協力の促進、南極地域における領土権主張の凍結、南極地域に関する共通の利害関係にある事項について協議し、条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催、などを主な内容としています。
南極条約締結国は現在47ヶ国で、そのうち、南極に観測基地を設けたり、科学調査をしたりするなど、積極的な活動を行っている28カ国は南極条約協議国と呼ばれ、定期的に協議国会議を開いています。
これまでこの協議国会議では、南極の環境や生物資源を具体的に保護するため、200以上の勧告、措置及び条約を採択してきました。これらの南極条約下で採択された勧告、措置及び条約を総称して「南極条約体制」と呼びます。具体的に挙げると、「南極のあざらしの保存に関する条約」、「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」「環境保護に関する南極条約議定書」などがあります。
さらに日本では「南極条約議定書」の締結にあたり、国内法として「南極地域の環境保護に関する法律」を1998年に整備しました。この取り組みにより、日本人が南極を訪れる場合には、特定の活動を除くすべての活動について、環境大臣に届出を行い、確認を受けることが義務づけられました。
南極条約は2009年に締結50周年を迎えました。南極を本来の姿のまま平和利用し、未来へ引き継ぐために、南極条約は、今後も守っていかなければならないものなのです。