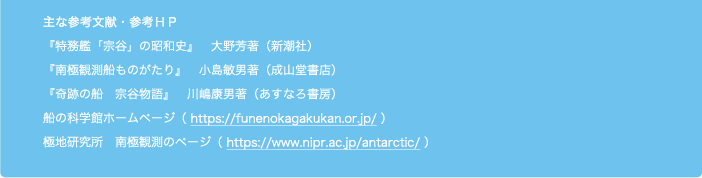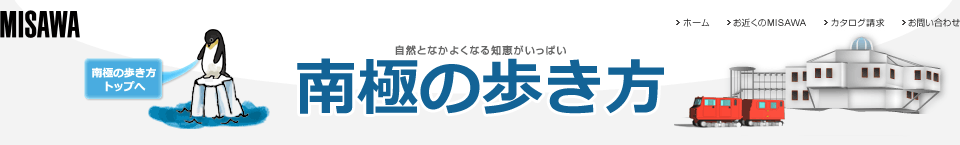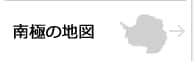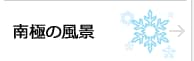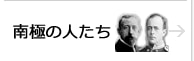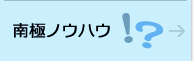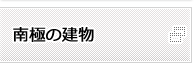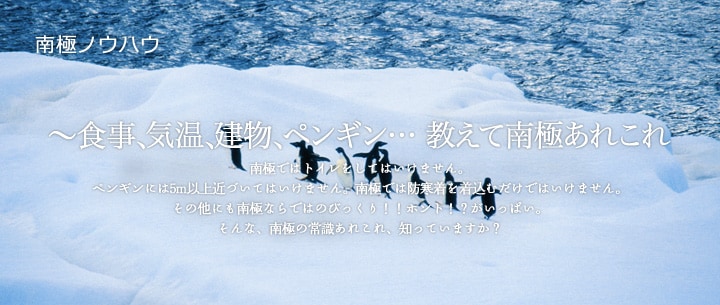

 そもそも宗谷は、南極観測を目的として製造された船ではありませんでした。それもそのはず、日本が南極観測参加を決めたのは1955年(昭和30)12月で、実際に南極大陸へ向かい出発するのは翌年11月の予定でしたから、船を一から造るのに十分な準備期間が無い状況でした。併せて、造船費として用意出来る資金も少なく、砕氷船の新造や外国船のチャーターなども検討されましたが、折り合いがつきませんでした。そこで候補に挙がったのが、海上保安庁の保有していた灯台補給船(各地の灯台を回って灯台守たちの生活品を供給する船)「宗谷」を改造して南極観測船とする案でした。
そもそも宗谷は、南極観測を目的として製造された船ではありませんでした。それもそのはず、日本が南極観測参加を決めたのは1955年(昭和30)12月で、実際に南極大陸へ向かい出発するのは翌年11月の予定でしたから、船を一から造るのに十分な準備期間が無い状況でした。併せて、造船費として用意出来る資金も少なく、砕氷船の新造や外国船のチャーターなども検討されましたが、折り合いがつきませんでした。そこで候補に挙がったのが、海上保安庁の保有していた灯台補給船(各地の灯台を回って灯台守たちの生活品を供給する船)「宗谷」を改造して南極観測船とする案でした。
しかし、ただの補給船であった宗谷がなぜ南極観測船に選ばれたのでしょう?
それは、宗谷の誕生にひみつがあります。
宗谷は、1938年(昭和13)に耐氷型貨物船として建造されました。耐氷型というのは、流氷のある海域を航海することを目的としているもので、そのときの船名は、「ボロチャエベツ」。ソビエト連邦から注文を受けて、造船された船でした。しかし、諸処の事情によりソビエト連邦に納品されず、引き取った日本の企業が「地領丸」という名前を付けて、樺太から朝鮮、台湾、中国の間などで資材を運ぶ輸送船として使うことになりました。
その後は、太平洋戦争の開始に伴い、旧海軍の特務艦(艦艇の助けを行なう船)となり、名前も北海道北端の「宗谷海峡」から取られた「宗谷」と命名されました。戦時中は座礁や魚雷による攻撃で沈没してもおかしくない危機に何度も遭いましたが、奇跡的にほとんど傷を負うことなく終戦を迎えました。終戦後は引楊船として主に樺太にいた日本人を本土へと運ぶ役目を果たし、そしてその任も終わると灯台補給船となったのです。
このような経緯のある宗谷でしたから、灯台補給船とはいえ、南極へ向かう基本能力を持っていた船だったのです。
 1955年(昭和30)12月に南極観測への参加表明を行ない、続いて「宗谷」改造の予算が決まると、宗谷を南極観測船(砕氷船)にする計画がスタートしました。日本と南極を往復するのに必要な能力を1年弱のうちに装備するというこの計画は、基本案を海上保安庁が立案し、それを日本の学界、造船界の権威者が具体的に練り上げ、詳細な図面は元海軍の技術者が組織した協会が請け負うという日本の英知を集結するといった取り組みで、氷の海を進むのに必要な「砕氷能力」を厚さ30センチから1メートルに上げること、同様に氷の海に閉じ込められても船体が浮くようにするために船の両側面にバルジと呼ばれる膨らみを設けることなどを主なポイントとして進められました。船を進める機動力には、それまでの古い蒸気エンジンから2,400万馬力のディーゼルエンジン2基にすると共にスクリューも2軸に変更、さらに、小型ヘリコプターを2機分の格納庫とヘリの離発着をする甲板が設置されるなど、宗谷は南極観測船へと姿を変えていきました。
1955年(昭和30)12月に南極観測への参加表明を行ない、続いて「宗谷」改造の予算が決まると、宗谷を南極観測船(砕氷船)にする計画がスタートしました。日本と南極を往復するのに必要な能力を1年弱のうちに装備するというこの計画は、基本案を海上保安庁が立案し、それを日本の学界、造船界の権威者が具体的に練り上げ、詳細な図面は元海軍の技術者が組織した協会が請け負うという日本の英知を集結するといった取り組みで、氷の海を進むのに必要な「砕氷能力」を厚さ30センチから1メートルに上げること、同様に氷の海に閉じ込められても船体が浮くようにするために船の両側面にバルジと呼ばれる膨らみを設けることなどを主なポイントとして進められました。船を進める機動力には、それまでの古い蒸気エンジンから2,400万馬力のディーゼルエンジン2基にすると共にスクリューも2軸に変更、さらに、小型ヘリコプターを2機分の格納庫とヘリの離発着をする甲板が設置されるなど、宗谷は南極観測船へと姿を変えていきました。
そして、1956年(昭和31)11月8日、南極観測船化を終えた「宗谷」は、南極へ向けて出発しました。
その後、無事に第1次南極観測を終えて帰国した「宗谷」は日本初の南極観測船として幾度かの修理と改造を施しながら、1962年(昭和37)4月まで、6次にわたる南極観測に活躍し、次の南極観測船「ふじ」にその任務を引き継ぎました。