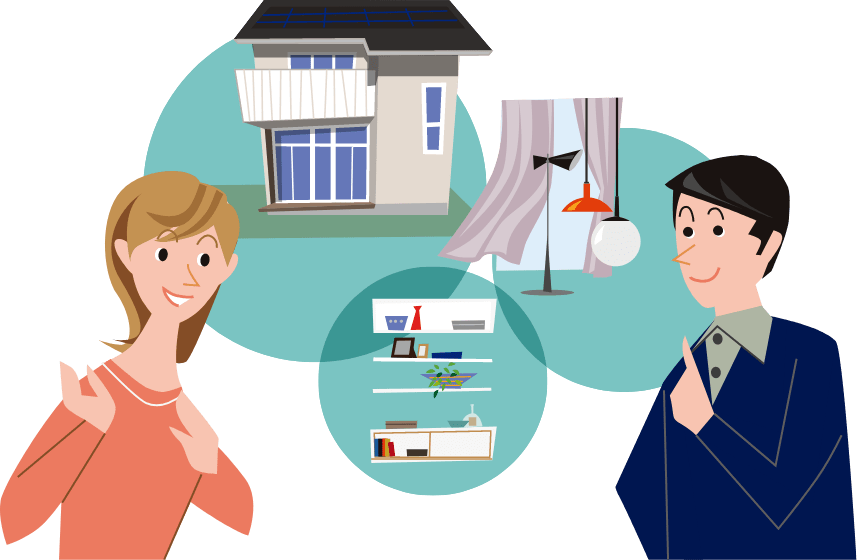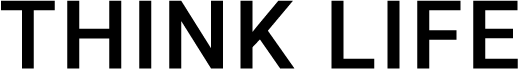interview
南極移動基地、
標高3,810mへ。
月面基地を見据えて
ミサワホーム かぐやプロジェクトメンバー
福田 真人さん(写真左)
吉崎 遼さん(写真右)
2019年11月に、「南極移動基地ユニット」が、
昭和基地に向けて出航した。
最終目的は、南極大陸・標高3,810mの地での
「持続可能な住宅システム」の実証実験だ。
そして、そこで培われた技術は、
月面の有人拠点開発に役立てられようとしている。
-

-
- JAXA宇宙探査イノベーションハブへ参加
- [吉崎さん] はじめに、「JAXA宇宙探査イノベーションハブ※①」をご説明しますね。これは、JAXA※②が培ってきた宇宙探査技術と民間技術を応用・融合させることで、宇宙と地上の技術を発展させることを目的としています。2017年に、JAXAの「宇宙探査イノベーションハブ」が実施した研究提案募集に、ミサワホームの「持続可能な新たな住宅システムの構築」という研究提案が採択されました。そして、その参加を機に、ミサワホーム内に「かぐやプロジェクト」が結成されたのです。
南極で36棟の建物建設をサポートしてきた実績
[福田さん] ミサワホームは約半世紀にわたり、極地研※③を通じて南極に36棟の建物建設を担ってきました。私は越冬隊員として南極に滞在しましたが、地球上とは思えない厳しい環境です。それは月面とつながる部分があると思います。南極における長年の経験が、「宇宙探査イノベーションハブ」での研究開発に活かせると考えています。
先々を見据えたモノづくりが好きな会社
[吉崎さん] それに、ミサワホームは先々を見据えたモノづくりが好きな会社です(笑)。世界初のゼロ・エネルギー住宅®を発売しましたし、最近では電気や水を創り出すインフラ不要の家(自立循環型住宅)※④の実証を始めています。そういったDNAや実績が、「宇宙探査イノベーションハブ」に、そして「南極移動基地ユニット」の計画につながっていますね。
-

-
第57次南極観測隊 越冬隊員当時の福田さん(南極、昭和基地にて)
-

-
- 南極移動基地ユニット計画
-
[吉崎さん] ミサワホーム、ミサワ総合研究所、極地研、JAXAは、未来志向の住宅や月面の有人拠点への応用を目指して共同研究を進めてきました。そして、持続可能というテーマのもと、「簡易施工性」「自然エネルギーシステム」「センサー技術を活用したモニタリング」などの技術の検証を行うこととしています。そして、「南極移動基地ユニット」の計画が動き出したのです。
目指すは昭和基地、そしてドームふじ基地へ
[福田さん] 今回は、2020年は昭和基地で、2021年からはドームふじ基地で「南極移動基地ユニット」の実証実験を行います。南極の昭和基地は、最低気温マイナス45℃・風速60mという厳しい環境です。さらに、そこから1,000kmほど離れた標高3,810mに、ドームふじ基地は位置しています。最低気温マイナス79℃を記録したことがある地です。地球のなかでも最も過酷な環境と言えるでしょう。
未来の地球を知るために
[福田さん] ドームふじ基地では、観測隊が氷床を掘り進めて氷のサンプルを調査します。2007年の調査では最深部の3,035mの氷のサンプルの掘削に成功しました。その氷には72万年前の空気が閉じ込められていました。それらを分析することで、地球の過去と現在との変化を分析し、未来を予測するのです。2021年からは第3期ドームふじ氷床深層掘削計画が始まります。その時に「南極移動基地ユニット」を居住空間として利用します。
-

-
南極移動基地ユニット輸送時のイメージ
-

-
- 最低気温マイナス79℃へ耐える
- [吉崎さん] 昭和基地での建物建築の実績がありましたから、構造体には自信がありました。しかし、問題は気温でしたね。マイナス79℃という気象条件は経験がありませんでした。たとえば、気密材として国内で使用される樹脂材は、マイナス50℃でガラス化してしまうので使うことができません。そこでシリコンゴムなど、住宅で使われてこなかった素材を試して、採用しました。多くの難問を抱えながら、メンバーと一緒に解決してきましたね(笑)。
拡張・縮小するユニット
[福田さん] 次に、サイズも問題でした。南極へ輸送する条件は、コンテナサイズです。しかし、そのサイズでは居住空間としては狭すぎました。そこで、ユニットを拡張・縮小するというアイデアが生まれました。釘も接着剤も使わずに、ボルト接合のみで組み立てられるように設計しています。使用する工具はラチェットレンチのみです。この技術はJAXAと一緒に開発していて、月面基地建設に活かすためのノウハウを蓄積することも目的にしています。
2020年3月から実証実験がスタート
[吉崎さん] 2020年3月から実証実験がスタートします。簡易施工性をはじめ、断熱性や気密性の維持。太陽光発電や集熱蓄熱システムなどのエネルギー利用の最適化。さらには、温湿度やCO²検知、火災検知などの見守りセンサーによる住空間の安全性や快適性などの検証です。私たちは、日本に送られてくるデータを見ながらの分析や今後に向けた開発を始めます。
-

-

-
南極移動基地ユニットの拡張・縮小が繰り返し可能
-
- 「持続可能」は、未来住宅のキーワード
- [吉崎さん] 今回の実証実験を行う「持続可能」というテーマは、未来住宅の要件と同じです。現在の日本では人口減少や資源枯渇、気候変動などの課題を抱えています。だからこそ、簡易に建築できて、省エネで、快適に安全に暮らせる住まいの必要性が増しています。さらに言えば、災害時の避難住宅や二地域居住など、今回の実証実験を、さまざまな可能性に応えられる未来住宅につなげていきたいですね。
その技術は、日本の住まいへ活かされる
[福田さん] 南極基地の性能は、日本の住まいと比べると一歩も二歩も進んだスペックになっています。最近では時代とともに、求められる住性能が高まっています。これまでも南極で培われた技術が、日本の住まいに取り入れられてきました。さまざまな技術やノウハウがお互いに行き来してきたのです。「南極移動基地ユニット」は、その先に月面基地を想定しています。その新しい挑戦は、必ず日本の住まいに活かされていきますので、お楽しみにしてください。
注釈
※①JAXA宇宙探査イノベーションハブ/JAXAが国立研究開発法人科学技術振興機構から「イノベーションハブ構築支援事業」(「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーションハブ」)に関する研究提案募集の受託を受け、地上の優れた技術を宇宙探査技術と融合させることで、宇宙開発のみならず、新たな産業創出による日本の産業振興を目指し、2015年にJAXAは「宇宙探査イノベーションハブ(TansaX)」を発足させました。
※②JAXA/国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
※③極地研/大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所
※④株式会社ミサワホーム総合研究所と沖縄科学技術大学院大学は、「蒸暑地サステナブルアーキテクチャー」にて、2019年度グッドデザイン賞(主催 公益財団法人日本デザイン振興会)の「グッドデザイン・ベスト100」に選定されました。受賞については、ミサワホーム株式会社と株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所を加えた4者での共同受賞となります。
-
-
南極移動基地ユニットの紹介
-

profile

- 福田 真人(写真右)
- ミサワホーム株式会社 技術部 耐久技術課 第57次日本南極地域観測隊 越冬隊員 入社後6年間は営業を経験、その後6年間は技術部で技術開発を担当、南極の自然エネルギー棟や基本観測棟などの設計を手掛ける。2015年から日本南極地域観測隊として1年4ヶ月、南極で勤務。極地での滞在経験を活かして、かぐやプロジェクトに参加。
- 吉崎 遼(写真左)
- ミサワホーム株式会社 商品開発部 施設設計課 技術部 かぐやプロジェクト 入社後13年間は商品開発部で鉄骨ユニットの開発に従事。工業化が進んでいる鉄骨ユニットのノウハウを活かすべく、かぐやプロジェクトに参加。
information

- 南極の歩き方
- 南極の基礎知識や昭和基地周辺のウォークビュー、南極観測隊参加経験のあるスタッフによる出張授業「南極クラス」など、南極を知るためのポータルサイトです。
webサイト