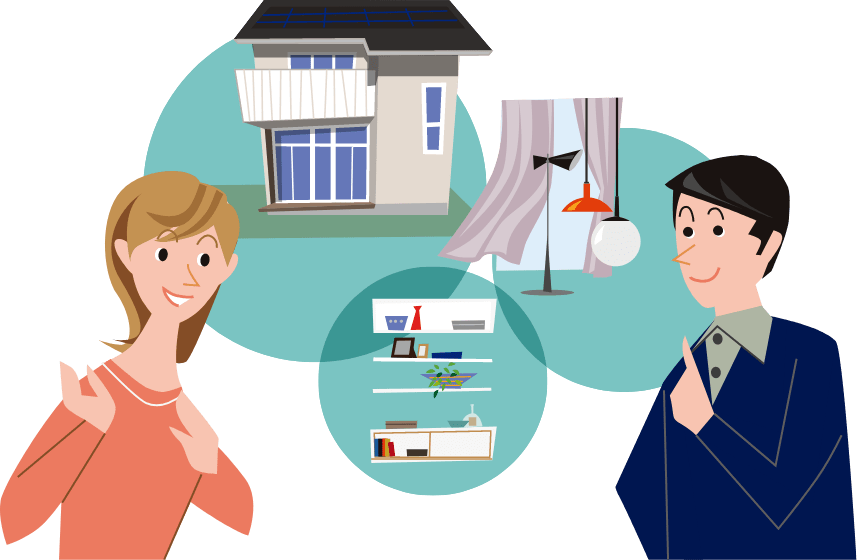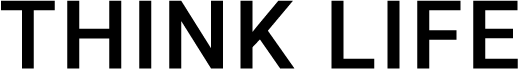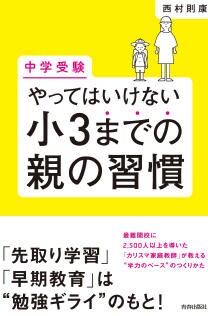interview
ステイホームを機に
親子でつくる学び習慣
プロ家庭教師
西村 則康さん
「伸びる子どもには
共通する学び習慣があります」と
難関中学校に2500人以上を合格させてきた
プロ家庭教師の西村さん。
ステイホームを機に目指すべき理想を伺った
-

-
- 子どもにもっと自由を
-
最近の子どもには、自由が与えられていません。小学校に入る前から、「このようにやりなさい」と指示され続けています。幼いころから勉強をさせられるなどして、夢中になって遊ぶ時間を持てていないんです。
成長に合わせて必要な学びがあります
大前提として、子どもには成長に合わせて必要な学びがあります。幼児期には体験学習、小学校低学年は基礎訓練、小学校4年生くらいから応用学習の時期に入ります。その時々に必要な過ごし方があります。特に小学校低学年までの遊びや学びが、その先の学力のベースとなるので、とても重要ですね。
-

-
- 幼児期は、五感を使った遊び
-
幼児期は、五感を使って遊ぶことが大切です。土を触れば、その感触だけでなく温度や湿度などが分かります。原っぱのある公園では、草の萌える匂いをかいだり、風のそよぎを感じたりできます。そういう体験が、小学校で学ぶ準備となるのです。
夢中になって遊ぶことが大切です
パズルで遊んでいた子どもは平面図形に強い。積み木をよくやっていた子どもは立体図に強い。幼いころに手先を使って遊んでいると、頭の中でいろんなものを動かせるようになるのでしょう。音楽でもプラモデルでも、夢中になって遊ぶことが大切です。夢中になると考えて工夫します。将来のためにも、幼児期にはそういう遊びが必要なんですね。
-
- ミサワホームの「ホームコモンズ設計」
- 子どもの成長に合わせて
4つの学び空間をデザイン 
-
・1st STEP(0〜1歳)
スキンシップで五感をはぐくむ
・2nd STEP(2〜6歳)
会話を通して想像力を伸ばす
・3rd STEP(7〜12歳)
興味・関心から意欲を伸ばす
・4th STEP(13〜21歳)
親子一緒に思考力を高める
-
- ステイホームでは、親子で体験を楽しもう
- 家族で料理するのもいいですね。キッチンは子どもにとって知恵と経験の宝庫です。野菜には浮くものと沈むものがある。塩をかけると野菜から水が出て小さくなる。水よりお湯のほうが、砂糖が溶けやすい。そういった体験が、理科での学びにつながっていきます。
好奇心を育てるのは親の役目です
子どもが「どうして野菜が小さくなるの?」と聞いてきたら、「いい質問ね」と笑顔で答えてあげてください。好奇心を育てるのは親の役目です。その反応が重要であって、答えはどうでもよくて「お母さんも分からないけど分かったら教えてね」でいいんです。「なぜ」と考えることが「いいことなんだ」と思ってもらうことが大事です。
「分かると楽しい!」という快感
難関中学校の入学試験では、創意工夫をする力‥‥もっと言うと試行錯誤する力が求められます。それは、ごちゃごちゃした世界への対応方法‥‥社会を生きていくうえで必要な力です。その原点は、子どもたちが絶対に持っている「なぜ?」という好奇心です。それは「分かると楽しい!」という快感につながります。そして、その快感を知っていれば、自ら創意工夫して学ぶことが楽しくなります。
-

-
- 基礎訓練は、読み書きそろばん
- 小学校の低学年では、基礎訓練をやっておかなければなりません。読み書きそろばんですね。地頭がいい子どもは、ここができています。特に音読は大切です。大人でも難しい文章になると、視覚的に読むのではなく、頭の中で「ぶつぶつ」と言いながら、音声を意味に変換して理解しています。こういう読み方ができないと、試験の重要な問題の意味が取ることができません。他にも、音読は先を読む力や一字一句を飛ばさずに読む力を伸ばします。
音読につきあってあげてください
ぜひ、ニコニコしながら音読につきあってあげてください。それだけで、子どもは「お父さんやお母さんが、喜んでくれている」とうれしくなります。「上手だねー、すごい」と褒める。それだけで音読は上手になっていきます。
-
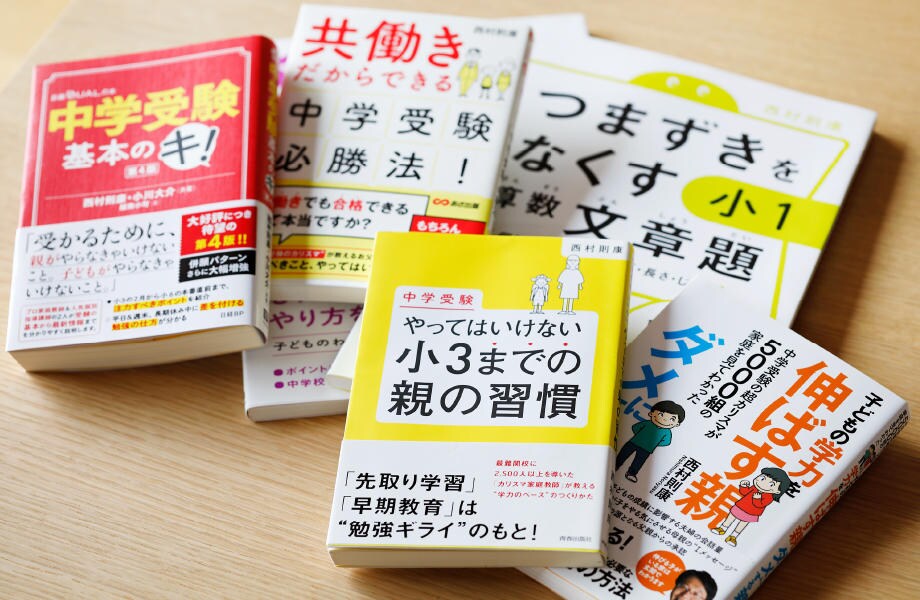
-
- ダイニングで学ぶのがいい
- 子どもは褒めるほどに伸びていきます。だから、学ぶのはダイニングがいいですね。親は褒めやすいですし、子どもは親を感じて、安心して学ぶことがでます。テレワーク中であれば、親が真剣に仕事をしている姿を見せるのは、とてもいいですね。「集中とは、どういうものか」を学んだり、学びの先にある働くことを考えるきっかけになると思います。
がんばる過程を褒める
できたことより、「努力しよう」や「がんばろう」としている過程を認めてください。子どもが創意工夫することを誉めてください。在宅時間が長ければ、やりやすいのではないでしょうか。うまく行かない家庭の親は「宿題はできて当たり前」と思っているから、子どもは終わっても褒めてもらえないし、やっているときは無視されています。
-
- 社会を学ぶチャンスに
- 時には、子どもと「新型コロナは大変だ」みたいな話をするのが大事ですね。「外出自粛と経済活動」は、二律背反の現象を考えるのにちょうどいい‥‥社会を学ぶチャンスです。子どもが好奇心を持って考えることを、楽しめるようにしてあげてください。
本当の意味での学び
私は「なぜ?を大事にして、創意工夫する力」を高めることが、本当の意味での学びだと考えています。ステイホームを機に「どんな大人になってほしいのか」というゴールを考えて、親子で学び習慣をつくってほしいと思います。
-

profile

- 西村 則康さん
- 40年以上、難関中学、高校受験指導を一筋に行う。暗記や作業だけの無味乾燥な受験学習では効果が上がらないという信念から「なぜ」「だからどうなる」という思考の本質に最短で入り込む授業を実践している。また、学習指導だけでなく、受験を通じて親子の絆を強くするためのコミュニケーション術もアドバイスする。著書は「子どもの学力を伸ばす親、ダメにする親(KADOKAWA)」、「中学受験は親が9割(青春出版社)」など多数。
関連サイト
名門指導会