interview
在宅避難のための
続けられる備えの話
防災士・管理栄養士
今泉 マユ子さん
「備蓄という言葉に身構えずに、
日常のストックが、災害時に役立つと
意識を変えることが大切です」
そう教えてくれた今泉さんに、
続けられる備えの話をインタビュー
-
- 在宅避難を前提に
-
最近、ニュースなどで在宅避難を聞くようになったと思います。もともと全国的に避難所の数が少なかったのです。そのうえ、避難所で確保すべき生活環境を定めた国際基準「スフィア基準」を順守する動きがあり、ますます避難所の不足が明らかになっています。これからは、危険な場所でなければ、在宅避難を前提に考えていただくのがよいですね。
やっぱり自宅がいい
昨年の能登半島地震で被災された方にお話を聞くと、多くの方が「やっぱり自宅がいい」‥‥「半壊していても自宅に戻りました」という方がいました。避難所の環境は場所によって大きく異なり、希望する避難所を選べない場合もあります。だからこそ、自宅で安全に過ごせる準備を整えておくことが、災害時の安心につながります。
-

-
- 備えについて考えてみる
-
在宅避難のためには、まずは命を守る備えが大切です。耐震性能の向上や家具やテレビなどの転倒防止など自宅を安全な場所にすることです。それができてから、次に健康を維持する備えです。食べ物、灯り、衛生用品、情報収集するものは絶対に必要‥‥調理にはカセットコンロとカセットボンベが必要、停電時にはポータブル電源が役立つ・・・ご家族で「もしもの時に必要なものは?」と、連想ゲームのように書き出してみてください。
灯りを忘れがちです
真っ暗の家で寝室からトイレに行って、実際に用を足してみると、その不便さがよくわかります。特に最近の子どもたちは暗闇に慣れていませんから、停電になるとパニックになりがち。だから、各部屋にポータブルライトを確保してほしいですね。蓄光テープを貼っておくと、停電時でもすぐに見つけられて安心です。停電時に自動点灯するライトもお勧めです。
スマートフォンは使えない前提で
災害時には、スマートフォンは使えない前提で考えたほうがいいですね。2019年に台風15号19号が上陸した千葉県では携帯3社の基地局が停止し、通信が途絶えました。災害発生時に情報を得られないのは、大きな不安とストレスにつながります。だから、ラジオは必需品です。それに電子マネーは停電すると使えなくなる場合もあるため、お札と小銭といった現金の備えも必要です。
-

-
- 備蓄ではなく、フェーズフリーを
-
いつも使っているものを、災害時に当たり前のように使えるようにする‥‥フェーズフリーという考え方をお勧めします。「災害のために特別なものを買わなければ‥‥」と思う方も多いですが、自宅にあるお米やパスタ、お餅も立派な備蓄なんです。いつもの食材が、もしもの時に役立ちます。日常的にストックをしておけば、ステイホームや急な体調不良の時にも安心です。
レトルト食品は災害時にも役立ちます
スーパーなどで買えるレトルト食品や缶詰、瓶詰、乾物、パウチのゼリーなどは長期保存できます。他にも、この「ずっとおいしい豆腐」はおいしいうえに常温保存可能、賞味期間が157日もあります。家族がいつも食べているレトルト食品は、災害時にも役立ちます。多くのレトルト食品は温めても、そのままでも食べられるため安心です。それに食べ慣れた味は、非常時の心の支えにもなります。
コーヒー一杯で日常を取り戻す
「災害時は我慢するものだ」と思われがちです。避難所では、出されるものをありがたくいただくことになるでしょう。でも在宅避難の備えは自分のためなので、自分が好きなものを備えておくことが大切です。毎朝、コーヒーを飲む方は、その一杯を災害時にも飲めるように準備しておきましょう。コーヒー一杯で日常を取り戻すことができます。
-

-

-
写真は、まゆまゆHokkori玄米ごはんシリーズ(賞味期限1年6ヶ月)「宮島醤油株式会社」。ずっとおいしい豆腐「さとの雪食品株式会社」
-
- ローリングストックを続けるために
-
これからは、食材を多めにストックしておいて、使ったら買い足していくローリングストックを習慣にしましょう。まずは、ストックを見えやすいように収納する。そして賞味期限の見える化です。我が家の場合は賞味期限の近いものを左に置くようにしています。また、その棚に黒マジックを置いて、賞味期限を書くようにしています。床下収納にはアルファ化米やパンの缶詰などを賞味期限別に分けてカゴに入れることで、管理がぐっと楽になります。
一度に大量に買わないように
災害が発生すると、不安から防災用品や水などをまとめて買ってしまいがちです。でも、そうすると一度に賞味期限や使用期限が切れてしまいます。たとえば、カセットコンロは本体10年以内、ガスボンベは7年以内の使用が推奨されています。そういう意味でも、定期的に使って、買い足していくのがいいですね。
-

-
写真上・左下は、大収納空間「蔵」®の備蓄イメージ、写真右下はローリングストック収納イメージ(すべてMISAWA-LCP - 防災・減災住宅より)
*大収納空間「蔵」は、ミサワホーム株式会社の登録商標です
-
- 防災ごっこ、停電ごっこ
-
毎月、防災ごっこを楽しんでほしいです。実際に体験することで、備えの不足が見えてきます。それに、失敗することで、次にどうしようかと試行錯誤して、工夫する力が育ちます。たとえば、停電ごっこ‥‥照明を消してポータブルライトで食事をしてみる。子どもは、最初は嫌がっていても、その後は楽しくなって「また暗闇ごはんをやろう」と非日常を楽しむようになります。こうした経験は、実際に停電が起きても、慌てず対応できる自信につながります。
一日前プロジェクト
内閣府のホームページに「一日前プロジェクト」というページがあります。「災害の一日前に戻れるとしたら、あなたは何をしますか」と、災害に遭われた方々に問いかけています。災害の種類別に、地域ごとに検索できるので、ぜひ読んでみてください。防災が自分事になり、「自分だったらどうするだろう?」と考えるきっかけになります。ぜひ、ご家族で見ることをお勧めします。
profile

- 今泉マユ子さん
- 防災士・管理栄養士・日本災害食学会災害食専門員。株式会社オフィスRM 代表取締役。管理栄養士として大手企業社員食堂、病院、保育園に長年勤務。食育、災害食、SDGsに力を注ぎ、2014年に管理栄養士の会社を起業。レシピ開発を行い、防災食アドバイザーとして全国で400以上講演を行う。著書は「かんたん時短、『即食』レシピもしもごはん(清流出版)」「免疫力アップレシピ もしもごはん3 災害時も、普段も、役立つ『お湯ポチャ』調理(清流出版)」など23冊。
関連サイト
オフィスRMー今泉マユ子-





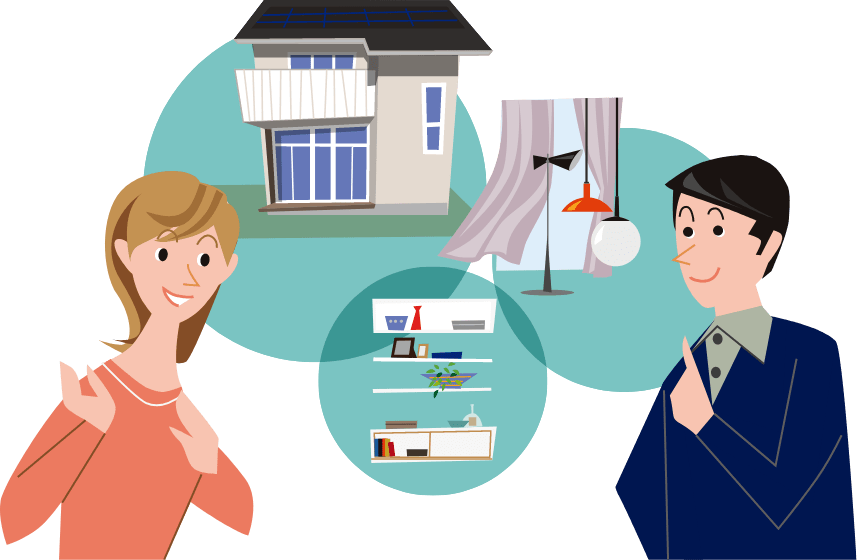




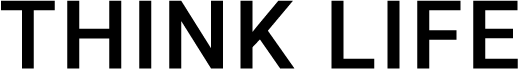

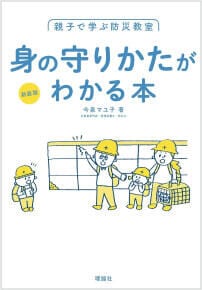

![ミサワホームの防災住宅 [1]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_02t.jpg)
![ミサワホームの防災住宅 [2]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_03t.jpg)
![ミサワホームの防災住宅 [3]](https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/img/2507_04t.jpg)



